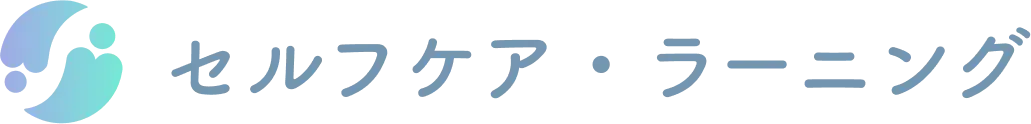保育現場のための
コミュニケーション改善リソース
伝え方・聴き方を変えると、職場が変わる
福祉現場特有のコミュニケーション課題を解決するための情報を無料で提供しています

保育現場のための
コミュニケーション改善リソース
伝え方・聴き方を変えると、職場が変わる
福祉現場特有のコミュニケーション課題を解決するための情報を無料で提供しています
なぜ、職員同士のコミュニケーションを学ぶ必要があるのか?
保育者一人ひとりが子どもにとっての「環境」であり、「安心・安全の環境」をつくるには、保育者自身が安心して働けていることが大切です。
また、チーム保育を実践するためには、「円滑な連携」が求められ、報告・連絡・相談が出来ていることが欠かせません。
しかし一緒に組む相手と「合う・合わない」という先行条件があるのも事実です。
「合わない」相手と働くには、高い柔軟性と適応力が必要となりますが、誰もがそれを有しているわけではありません。合わない相手と関わる日々は、ストレスと忍耐が増え、好転の見通しが立たなければ、今の職場を辞めて他の職場へ行きたいと考えはじめます。
こうして毎年の年度末~翌年度始めにかけて、大量の職員が転職によって働く場所を変えています。求人倍率が高いことから、転職はそれほど難しいものではなく、人材紹介会社が提示する紹介料も年々高くなっています。
保育施設を運営する各法人にとって、「採用コスト」の高騰は悩みの種であり、採用した人材をいかに自社で長く活躍してもらえるかについて、試行錯誤を続けています。
職員と会社とのエンゲージメントを高め、定着率を上げるために、「コミュニケーションスキルを学ぶ」という選択肢は取りやすく、各社の研修担当者さんは、年間計画を立てて、各階層に合わせた研修カリキュラムを構築しています。
子ども一人ひとりの成長段階に合わせた、より適切な保育を展開していくためには、子どもとの信頼関係はもちろん、職員同士の信頼関係が絶対に必要だと言えます。
お互いが尊重し合える関係をつくるには、普段から積み重ねているコミュニケーションの質が重要となります。
実は大半の職員が、肯定的な関わりを積み重ねる努力をしているのですが、その努力を上回るストレス(人手不足、業務過多、難しい保護者対応等)がかかり、心身の余裕がもてず、つい望ましくないコミュニケーションを取ってしまうことが少なくありません。
さらに生真面目な方は、そんな自分自身を否定してしまい、一時的に自己肯定感を低下させてしまいます。また、同僚の保育に対して、「指摘すること」が苦手だと感じている方がとても多く、「それはちがうと思う」と言えないことが、保育の質を高めづらい要因にもなっています。
このような苦境を乗り越えるためにも、「コミュニケーションスキルを学ぶ」という選択肢はとても有効です。
普段「後回し」にしてきた自分自身を振り返り、肯定的な関わりの大切さを「再認識」することができます。また、よりよい方向へ進むための「対話的コミュニケーション」学ぶことで、関係性を保ちながら「指摘」や「リクエスト」をする具体的な方法を学ぶことができます。やり方を知ったことで勇気と見通しが生まれ、前向きになれた方が沢山います。
現場で見られる主な課題
こうなるべき、こうするはず、といった自分の「あたりまえ」が、相手と異なることは多々生じています。仕事の進め方、分担の割り振り、負担の比重、報連相の範囲、締め切りや時間管理、休みの取り方、礼儀・マナーなど、例を挙げるとキリがありません。
柔軟性が高ければ、許容範囲が広いので、表立った問題にはなりませんが、ちがいを「受け止められない」心理に陥ってしまう方は、どの職場にも一定の比率で存在します。
この心理状態から、否定的なコミュニケーションが発信されると、組織レベルでの問題が生じてきます。
前職で培った保育観、保育士として初めて勤めた職場で培った保育観は、新しい職場に入ったときに「違和感」を生じさせることがあります。
さらに遡れば、自分自身が育った家庭環境で培われた保育観も、無意識下に抱いているものです。
施設全体で同じ方向に進もうとする中で、自分の保育観を否定されたような「違和感」があるとき、どのようにその想いを表現するかは、とても難易度が高いことでしょう。
適切に表現ができない状態が続くと、否定的なコミュニケーションが発信され、組織レベルでの問題が生じてきます。
職員関係では、親子のような年齢差があることも珍しくありません。5~10歳程度の年齢差でも、お互いの感覚に驚くような差を感じることが増えているようです。
日本の文化は「同質性(みんな同じ)」に慣れてきましたから、年長者が年少者に対して、異質な感覚を抱いて戸惑うのは無理もないでしょう。逆に年少者から年長者に対して感じる違和感もまた当然のものだと言えます。
異質な違和感に対処できないと、「レッテル貼り」や「決めつけ」が生まれがちです。「いまの若い人たちは・・」「上の人たちはみんな・・」といったセリフが増えると、「誰が悪いか」の視点が固定化してしまい、「ちゃんと話し合えない雰囲気」が出来上がっていきます。
保育現場は95%以上が女性で構成された集団です。
人類の歴史上、古来から女性という性は、「選ばれる側」に置かれてきました。どんな相手に選ばれるかで、生活の質が決まってしまう時代が長く続いてきました。そうした記憶は遺伝子やDNAに組み込まれて、生まれながらに受け継いでいるという説があります。
時代は大きく変わり、女性の社会進出、男女雇用機会の均等が常識となりましたが、「選ばれる側」の心理は、いまもなお残存していると思えて仕方ありません。
言い換えると、「外されないか?」「悪く思われないか?」「味方は誰か?」という心理からの行為が、頻繁に見受けられるのです。
例えば「一人になりたくない」という衝動は、自分の思いに同調してくれる相手を求めるものです。それが陰で特定の人を批判する行為(いわゆる陰口)を生じさせています。
それ以外にも、「嘘をつく」「無視する」「意地悪をする」といった行為が増えると、チームの心理的安全性が崩れていきます。
なぜこうした課題が改善されないのか?
自分の長年のクセやパターンがたった1つの選択肢だと思い込んでいるからです。
さらにそれが「正しいことだ」という信念が加わると、なお変えづらくなります。
また「コミュニケーションは性格で決まる」と誤解している人も多くいます。
コミュニケーションについて学ぶ機会がないまま大人になっているので、当然のことだと思いますが、「変えられない」「変える必要はない」という前提に立っていれば、同じ状況に翻弄されて疲弊する、あるいは周囲を翻弄し、疲弊させてしまうでしょう。
どうしたら改善されるのか?
各個人が「柔軟性」と「適応力」をいまより高めることに尽きます。
そのためにすべての職員が「コミュニケーションのスキルとマインドを学ぶ」ことです。
これは対人援助職としての「成熟度」を高めることだと言えます。他人と比べる必要はありません。過去の自分と比較して、1%ずつでも高まっていけばよいのです。
そして組織全体では、「肯定的な関わり」を粘り強く続けて、「肯定の貯蓄」を増やしていくことです。何も特別なことではなく、挨拶・笑顔・感謝・お詫びの4つを真摯に行っていくことが大切です。劇的な変化を期待せず、小さな成功体験を積み重ねていきます。
セルフケア・ラーニングの研修では、個人レベルと組織レベル、いずれの変化も起こせる研修プログラムを提供いたします。
コミュニケーションは「情報伝達」の手段であり、「受信(きき方)」「処理(とらえ方)」「発信(つたえ方)」の3つに分解することができます。
3つの「やり方」がアプリケーションだとすると、「あり方」がOSの役割になります。「あり方」は<こころのまなざし>と言い換えることができ、対人関係において、「自分や相手を何者とみているか?」を指しています。
例えば、相手を<仲間だ>と見ているのと、<敵だ>と見ているのとでは、受信、処理、発信の中身が全く変わります。
職場には、そもそも協力関係を築くために人が集まっているわけですが、あらゆるストレス要因によって、<こころのまなざし>が崩れることがあるわけです。
さらに人間には、本能的に避けたい相手がいたり、どうしても譲りたくない状況があったりします。
ですから<こころのまなざし>を安定させるには相当な「自覚」が必要です。
「無自覚」でいると、あっという間に崩れ、「向こうが悪い」といった対立の心理に陥り、適切な「やり方」を使えなくなってしまいます。
職員一人ひとりの心理構造は、ある意味「システム」のようなもので、OS(あり方)をアップデートしないと最新のアプリ(やり方)は動かせません。
だからこそ、計画的かつ継続的な学びによって、アップデート機会を作る必要があるわけです。
コミュニケーションおいて行き交うのは「情報」だけではありません。
もっと力強く行き交っているのが、「エネルギー」です(熱と言い換えても構いません)。
「エネルギー」は目に見えないが確かに存在し、とてもパワフルなものです。
保育士養成校の学生が、就職先を選ぶにあたって「先生たちの雰囲気がよい保育園がいい」と言いますが、この「雰囲気」がまさに「エネルギー」を指しています。
職員同士がコミュニケーションを取る度に、そこに「エネルギー」の交流結果が生じます。
心地よいのか、そうでないのか。いまの交流がどんな「エネルギー」を生み出したか、誰もが感覚的に理解していることでしょう。
あまり意識しないことかもしれませんが、「エネルギー」には3つの質があります。
「ポジティブ(+)」「ネガティブ(-)」「ニュートラル(0)」です。
ポジティブ(+)
楽しさ 喜び 感謝 など
ネガティブ(-)
否定 拒否 攻撃 など
ニュートラル(0)
安心 穏やか リラックスなど
あなたの所属する職場において、誰が、どんな時に、どの質のエネルギーを発しているか、想像してみてください。だいたいのイメージがつくと思います。
職場に良好な雰囲気を作り、働きやすい場にしていくには、みんなのエネルギー状態を良好に保つマネジメントが必要となります。
そのための第一歩は「セルフケア」です。自分の状態を良好に保つことが、何よりも一番大切なのです。
エネルギーは「共振・共鳴」します。これは科学的に立証されていることです。
自分がポジティブな状態であれば、周囲にポジティブな影響を与えることができます。
自分がネガティブな状態であれば、周囲にネガティブな影響を与えてしまいます。
自分がニュートラルな状態であれば、周囲がどんな状態でも調整役を担うことができます。
相手をああしたい、ああなってほしいと考えるのも無理はありませんが、まずはベクトルを自分自身に向けてみましょう。
自分が整うことで、必ずや望ましい方向への変化が起きます。
そのために「セルフケア」を自覚して、日常に取り入れることが有効です。その成果として、「あり方(こころのまなざし)」が整い、きき方、とらえ方、つたえ方が機能してきます。
すると必然的に、あなたから発せられるエネルギーが整い、周囲に良い影響をもたらすことになります。大げさに思える方は、「せめて、自分が合格点の状態でいればOK」と捉えておいてください。
コミュニケーションにおける「あり方」最初の1歩
相手と関わる30秒前くらいに、自分が相手を「何者と見ているか?」を自己点検し、図1のB欄に似た状態になっていないかを確認します。なっていたら、A欄の状態に置き換えようとしてください。
すぐに出来るときと、できないときがあるでしょう。すぐに出来ない、あるいは「到底無理だ」と思っていても、せめて「同じ人間」と見ます。そのうえでコミュニケーションを始めます。(「到底無理だ」と感じた場合は、改めて時間をとって、セルフケアを行う必要があります。)
内面に「つながる方向のまなざし」を持つと、非言語(表情、目線、声のトーン等)が適切になります。完璧でなくてOKですから、まなざしを「整えようとすること」自体に価値があるのです。
パートナー
協力者
協働者
力を合わせる相手
自分の鏡
自分の一部
同じ人間
敵
あっち側の人
格下、格上の人
困った人
冷たい人
意地悪な人
怖い人
とらえ方(処理技能)
「自分が正しい」という感覚は健康に生きていくうえで必要なものだと思います。
しかし、この感覚が強いとコミュニケーションにおいて、ネガティブなエネルギーを発信することに繋がります。多様性に対する理解が求められる現代は、自分の「正しさ」が通用せず、相手から敬遠され、自分も相手も苦しい状態に陥りやすいでしょう。
この時、自分が組織上の権限を有していたり、腕力が強かったり、表現に迫力があったり、集団内での影響力が強かったりすると、「力で勝つ」ことが出来てしまいます。
ここが注意点です。自分の「正しさ」を「押し通すこと」が出来てしまうのです。この時、その集団はネガティブなエネルギーで疲弊します。
ですから、あなたの「力が強い」ならなおさら、「正しさ」を降りましょう。
そして「正しさ」ではなく「適切さ」を目指しましょう
コミュニケーションにおける「適切さ」は、2つの尺度で測定します。
1つ目は「意欲が高まったか?」2つ目は「関係が保てたか?」です。
それを伝えることで、相手は「やろう/やってみよう」と思えたでしょうか。
それを伝えることで、お互いは「話せた/また話せそう」と思えたでしょうか。
常に「適切さ」を目指して関わるというとらえ方は、時間をかけて熟成していくものです。
「正しさ」を降りるのが怖い、どうしても譲れないという抵抗感がある場合は、アンガーマネジメント等、別途効果的なトレーニングを行えば、少しずつ好転していきます。
職場の人間関係において、価値観のちがいは当然に起こるものです。
その都度、必ずネガティブな反応を示すかというと、そうでもありません。
人によって、又は場面によって、「あり方(こころのまなざし)」の状態が異なるためです。
良好な状態であれば、「ちがい」に対して肯定的にとらえます。「ちがっていい」「ちがうのがあたりまえ」「ちがいって面白い」と考えるに至ります。
良くない状態であれば、「ちがい」を否定的にとらえ、「まちがい」にしてしまいがちです。
相手を「まちがい」にすると、「自分のほうが正しい」「相手のほうがまちがっている」という二極化が生まれ、エネルギーはネガティブとなり、関係性は「分離(ばらばら)」になるのです。
「保育は正解が1つではない」と多くの保育者が確信をもって言っています。
とすれば、相手の行為を一方的に「まちがい」と決めつけることは行き過ぎだと言えるでしょう(不適切行為とされるケースは例外)。
「ちがい」を「まちがい」にしない。このとらえ方を用いて、あらゆる職員と関わってみてください。
1つ補足ですが、正解を1つに決められることには、「まちがい」が生じます。
例えば、「8:00までに出勤」すべき日に「9:00に出勤」したら、これはまちがいですね。
ここでお伝えしているのは、保育のやり方、段取りの順番、報連相の範囲など、正解を1つに決められないことについてお話ししています。
きき方(受信技能)
相手の言ったことを受信した際、同意できないことがありますね。
自分にとって大事なことであればなおさら、即座に「ちがう」「いやだ」「やめて」と言いたくなるものです。すると、同意できないなら「反対する」というパターンが生まれ、自覚がないと、これが習慣になっていきます。
一方で、大半の職員の方は、自分のことを「わかってほしい」と願っているはずです。
「わかる」という意味には、「同意してもらう」だけでなく、「理解してもらう」という意味が含まれています。ですから、「わかってほしい」という願いには「同意してくれなくても、せめて、理解を示してもらいたい」という期待が込められているのです。
良好なコミュニケーションを通して、信頼関係を保っていくには、「受け入れられなくても、いったん受け止める」ことが重要です。
即座に「ノー」と伝えるのではなく、「~なのですね」と応答し、理解を示します。本心では「あれ、そうじゃないよな」と思考していても、まずはいったん受け止めましょう。
この行動が増えていけば、こちらが話し、相手も話すという双方向のコミュニケーションが増えていきます。粘り強く対話を続けていけば、決めつけや思い込みが外れて、お互いに新しい視点を生まれることも十分に有り得ます。「そうだよね」と同意できなくても、「そうなんだね」といったん受け止めて、理解を示すことを実践しましょう。
つたえ方(発信技能)
相手とのちがいに遭遇したとき、それが自分にとって大事なことであれば、「マイナス感情」が沸き上がってきます。マイナス感情は私たちの身体にとって「危険信号」となるため、脳は「戦うか?逃げるか?」の二択をしようとします。この状態で何かを伝えようとすると、ほとんどの場合において「相手」が主語になっています。
「あなたがやってくれない」「向こうが~」「あの人が~」という状態に陥るのです。
このまま発信に入れば、相手を責めるような、あるいは、何も言えずに黙る自分に落胆するような、いずれもネガティブなエネルギーが発せられるのです。
この時に私たちが取れる選択は「主語を私にすること」です。
まずは「相手が主語」になったことに気づいてください。そして少し間を取り、自分に対して問いかけます。
私にはどう思えている?どう見えている?
私はどんな影響を受けている?
私はどんな気持ち?
私はどうしたい?どうしてほしい?
こうした問いに対しての答えは、「私が主語」に置き換わっています。
それを落ち着いて発信すれば、情報の質が高くなり、「相手が主語」よりも、伝わる確率が高くなります。また、非言語も望ましい方向へ変化します。マイナス感情の責任を、「相手のせいにする」のではなく「自分で引き受ける」ことになるためです。
ここまで、強いマイナス感情を感じた場合を前提にお伝えしてきましたが、普段の落ち着いた状態のときから、「私は~」「私としては~」等、「主語を私」にして話す習慣をつけてみてください。自分も思いと言葉が一致した感覚も増えて、自己信頼を高めることができます。
職場での実践ポイント
小さなストロークを公平かつ一定にする
ストロークとは「働きかけ」のこと。この5つは、相手を尊重するストロークにあたります。
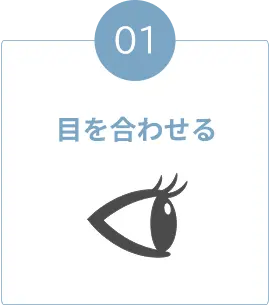
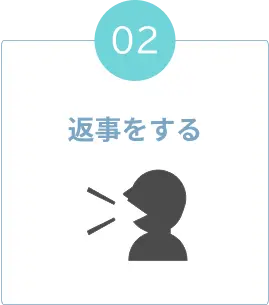

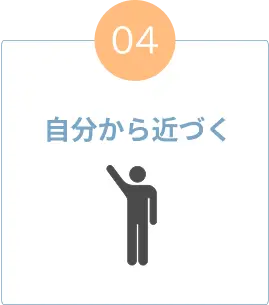

しかし、価値観のちがう相手には、無意識に減ってしまうことが多くあります。
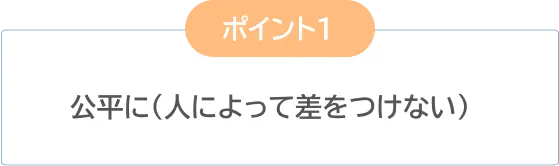
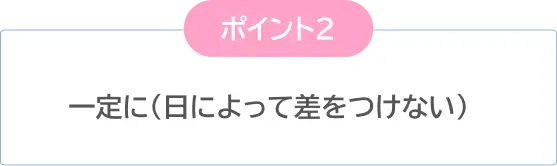
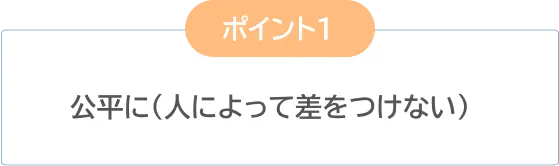
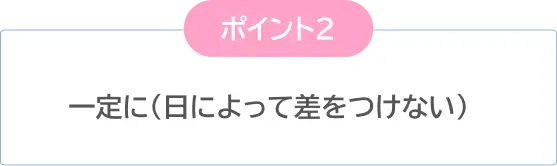
普段から「差がついていないか?」を振り返り、気づいたらバランスをとりましょう
あなたから出力されるストロークが安定しているほど、信頼感が高まります。
嫌な気持ちに折り合いをつける
01
気づく
「あ、モヤモヤがきたぞ」
02
みとめる
「させられたのではない、自分がモヤっとしてるんだ。モヤつく事自体はOKなんだ」
・「みとめる」ためには、「感じてOK」が必要です。
・嫌な気持ちは良くないものとしがちですが、感じることはOKです。
・また、感情は「させられた」と思いがちですが、そうではありません。
・「イライラさせられた」のではなく「イライラしている」が適切です。
03
力を抜く
「ふぅ~と息を吐いて、身体の力を抜く」
仕事中、嫌な気持ちになったとき、この3ステップを実践してください。
何度も繰り返すうちに習慣となり、感情のコントロール力が高まっていくでしょう。
主語を「わたし」にして話す
あなたは○○だ
あなたがしないから、迷惑している
あなたは、なんで~しない(しなかった)の?
わたしにはこう見えた/聞こえた/思えた
わたしは~という影響を受けている
わたしは~という気持ちだ
わたしは~してほしい
- 責めるのでも、黙って飲み込むのでもなく、「落ち着いて話す」ことができます。
- 指摘、意見、提案、要望、自己開示など、あらゆる場面で有効な伝え方です。
- 主語が「わたし」になることで、お互いの交流に「余白」が生まれ、相手も自分のことを話しやすくなります。
「対話しやすい風土」をつくり、職員同士の関係の質が向上していきます。