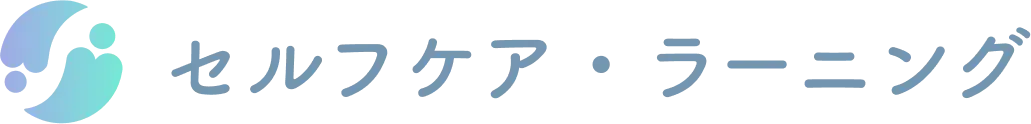Q:中里先生の研修との出会いは?
中里先生の研修と出会ったのは、2016年にこの会社に入社したタイミングでした。
それまで私は、自動車販売や家電量販店など、異なる業種で接客や人材育成の仕事をしてきたのですが、人と接すること自体は、自分でも得意だと感じていました。
ただ、中里先生の研修を受けたときに、それまで自分の中にあった“感覚値でやっていたこと”が、明確に言語化され、理論として整理されたんです。
それが非常に印象的で、「ああ、もしこの視点をもっと早くから持っていたら、これまでの接客の質もさらに高められていただろうな」と素直に思いました。
人と関わる仕事をしていくうえでは、こうしたスキルはやはり基本であり、核となる部分だと思います。
きちんと理解しておくことで、状況を俯瞰して見る力もつきますし、感情に流されずに落ち着いて物事に対処できるようにもなると思いました。
そうした学びは、保育園という現場においても、間違いなく実用性が高いし、応用がきく内容だと感じています。
Q:現場の職員さんと接していて、中里先生の研修の内容を、ふと思い出すようなことはありましたか?
ありますね。私が入社した当初は、大阪エリアの担当として、いくつかの園の現場サポートをしていたんです。
特に、職員全員との面談を年に2回実施していたので、現場の方々と向き合う機会は非常に多くありました。
そうした面談の場では、相手の話をただ聞くだけではなくて、その人の状態やタイプを俯瞰して見る視点が必要になります。
また、感情的な話になっているときも、「そのお気持ちはよくわかります」と一度しっかり受け止めたうえで、本来の課題に目を向けていくような対応を心がけていました。
こうした対応の基礎には、やはり中里先生の研修で学んだことがあったと思います。
研修を受けていなければ、たぶん私自身も、感情に引っ張られてしまっていた場面があったかもしれません。
あのときの学びが、自分の中で判断の軸や対応のバランス感覚につながっているのを実感しています。
Q:現場のサポートをするうえで、困りごとだったことはありましたか?
自分自身は、中里先生の研修を受けたことで、相手との考え方の違いに気づく視点や、感情を整理する力をある程度身につけてきたと思っています。
ただ、現場の先生方の中には、まだそこが十分に定着していない方もいて。
「どう伝えれば伝わるか」 という点で、悩むことは少なくありませんでした。
また、同じ社内の人間同士だと、やはりどうしても伝えづらいことがあるんです。
たとえば、「この伝え方はこう工夫したほうがいい」と言っても、“上司の意見”として受け取られてしまったり、構えられてしまったりすることがあるんですね。
だからこそ、外部の講師の方に話していただく意味は非常に大きいと感じました。
特に中里先生のように、現場を理解しながら、専門性を持って伝えてくださる方の言葉は、スッと心に届きやすいと実感しています。
さらに言えば、日々の会話の中で自分が使っている言葉と同じことを、講師の方が同じように研修で話してくださると、職員たちの中で「あ、やっぱりそうなんだ」と納得が深まるんです。
そうした“言葉の重なり”が、現場にじわじわと効いてくる感覚がありますね。
Q:外部の講師は、どんな講師が良いと思いますか?
保育現場で働いている方たちって、細やかな気遣いを大切にしていらっしゃる方が多い印象です。
だからこそ、たとえ自覚がなくても、いわゆる“バシッと言われる”ような指導には、少し構えてしまうところがあると思います。
理路整然と強めの口調で言われたりすると、それがどんなに正しいことであっても、「自分たちとは違う世界の話」として受け止められてしまいがちです。
それは決して受講者が未熟ということではなくて、現場の空気感や文化的な背景があるからなんですよね。
ですから、外部講師の方には、やわらかく、受講者の気持ちに寄り添いながら、丁寧に伝えていただける方であってほしいなと感じています。
その点で、中里先生はまさに適任です。
たとえばグループワーク後の発表の場面でも、発表している方は少なからず緊張されていますよね。
でも中里先生は、その発言をきちんと受け止めてくださったうえで、研修全体の内容と自然につなぎ合わせてフィードバックしてくださるんです。
それによって、発言した本人も「自分の言葉と学びがつながった」という実感が持てる。
結果として、理解の定着や納得感が深まるんですよね。
そういう講師のあり方が、現場にはすごく合っていると思います。
Q:中里先生と御社はもう10年目に入られますが、依頼し続けている理由は何ですか?
私たちの会社では、本当にさまざまな価値観や背景を持った人たちが集まってきています。
だからこそ、人と関わりながら働くうえで必要なスキルや考え方を、研修の入口でしっかりと伝えることがとても重要だと考えています。
中里先生が研修でお話しされている内容は、まさに人と人が一緒に働いていくうえで欠かせない基本的な土台になるものです。
特に、中途入社者研修やその後に続くシリーズ研修の中で、人と接する際に大切にしてほしい視点を押さえてもらえることが、私たちにとって大きな意味を持っています。
それが積み重なっていくことで、その“入口”をくぐった人たちが社内に少しずつ増えていく。
そして結果的に、社内の風土が少しずつ整っていくんだと思うんです。
また、その“入口の研修”を毎回同じ講師の方にお願いすることで、伝わるニュアンスがぶれずに、しっかりと浸透していくというメリットもあります。
そういう意味で、中里先生にお願いすることが一番良いと、私たちは思っています。
Q:他の講師と比べて、中里先生にお願いしてよかったと思う点はどこですか?
一番大きいのは、やはり長く関わっていただけているという点だと思います。
私たちの会社で採用している職員たちの雰囲気や傾向を、中里先生はすでに把握してくださっていると感じますし、それが研修の内容や伝え方にも自然と反映されているんです。
また、中途入社時の研修だけでなく、その後のフォローアップ研修も継続して担当いただいています。
ですので、中里先生は1年後、2年後の職員の状態も見たうえで、研修に臨んでくださっている。
その積み重ねがあるからこそ、他の講師の方にヒューマンスキルの研修を依頼する場合よりも、内容に深みがあると感じます。
さらに、私たち本部メンバーも、中里先生との年1回の個別面談を受けていて、そこで直接お話しさせていただく機会があります。
そうしたやり取りの中で、お互いに課題感を共有しながら、率直に意見交換ができる関係性が築けているのも、大きな安心材料のひとつです。
Q:年1回の面談を受けていて、何かプラスになっていることはありますか?
面談を受けていて実感するのは、自分の中にあるイライラやもやもやといった感情の正体を、中里先生との対話の中で引き出してもらえているということです。
普段の業務の中では、つい流してしまいがちな感情の動きについて、「自分は今、なにに引っかかってるんだろう?」と気づける機会になっていて。
それが整理されてくると、「これは冷静に対処しよう」と落ち着いて構えられるようになるんですね。
また、「自分はこう感じている」という自己認識があっても、それが本当に合っているのかどうか、自信を持てないこともあります。
そういうときに、中里先生から「ちゃんと見えてますよね」といった一言をもらえるだけで、気持ちの整理がぐっと進む感覚があります。
対話を通じて、自分を客観的に見る感覚が育っていくというのは、すごく大きなプラスだと思っています。
Q:研修内容で、記憶に残っている部分はありますか?
特に印象に残っているのは、「ちがい」と「まちがい」という言葉です。
初めて聞いたとき、自分の中で「はっ」とさせられました。
それまでは、たとえば職場で「なんでこの人はこんなことをするんだろう」と思ったとき、それをすべて“まちがい”として捉えてしまっていた自分がいたんです。
でも実は、それが自分のイライラの原因だったんだと気づいて。
この視点に出会ったことで、「ヒューマンスキル」というものにすごく興味を持つようになりましたし、もっと学んでみたいと思った最初のきっかけにもなりました。
それ以降は、「この人はこういうふうに感じているのか」と、違いをそのまま受け止められるようになってきたと思います。
そうすると、じゃあどういう言葉がけをしたらいいか、どんな提案ができるかという風に、思考の方向も変わっていきました。
もうひとつ印象的だったのが、「非言語」という言葉です。
正直、それまで聞いたことがなかったのですが、「たとえニコニコしていても、心の中では別の感情が表れていることがある」という話を聞いて、とても腑に落ちました。
現場の先生方と面談をしている中でも、まさにそういう“言葉にされていない表情や雰囲気”に気づく場面があって、「あ、これが非言語か」と現実の場面と結びついたんです。
あの学びがあったからこそ、より深く相手を見る意識が育ってきたのだと思いますが、まだまだ教わりたいことはたくさんあると感じています。
Q:中里先生への依頼を検討している方に、どんな言葉をかけたいですか?
もちろん、中里先生の研修そのものを受けることで、多くの気づきが得られるとは思います。
でも、個人的にはそれ以上に、中里先生と“ざっくばらんに話をしてみること”自体に、大きな価値があると感じています。
というのも、対話の中で見えてくるのは、今すでに表面化している課題だけではないんです。
自分でも気づいていなかったような、背景にある課題や思考のクセにまで自然とたどり着ける、そういう感覚があるんですね。
なので、「ヒューマンスキルをどう伝えよう」「コミュニケーションの課題をどう扱おう」といったテーマに興味を持っておられる方には、
“まず一度、中里先生と話してみてください”と、迷わずお伝えしたいです。
研修を依頼するうえで、それが最短で、そして最良のルートになると、私は思っています。
Q:最後に、ウェブサイトをご覧の方へ一言お願いします。
おそらく今このページをご覧になっている方は、自社の研修や人材育成のことで何か課題を感じておられるのだと思います。
そして、その課題の糸口を探す中で、このサイトにたどり着かれたのではないでしょうか。
もしそうであれば、まずは一度、今感じておられることを中里先生に直接お話しされるのが、一番の近道だと私は思います。
初めての方に何かを相談するのは、誰しも緊張するものですし、プレッシャーもあると思います。
ただ、私は仕事柄、外部の専門家の方とお話しする機会が多いのですが、その中でも中里先生は本当に話しやすい方だと感じています。
私自身が初めて中里先生とお話ししたのは、今から9年ほど前ですが、
そのときから「この人には、どんなことでも話して大丈夫だな」と自然に思えました。
実際にお会いして感じたその印象は、今も変わりません。
ホームページや写真だけでは、なかなか一歩を踏み出しにくいという方もいらっしゃると思います。
でも、私は声を大にして言いたいんです。「踏み出しても、ぜんぜん大丈夫な相手ですよ」と。
私自身、中里先生とお話しするなかで、視野が広がったり、見えてくるものがたくさんありました。
その経験を、ぜひこのページをご覧になっている皆さんにも、味わっていただけたらと思います。