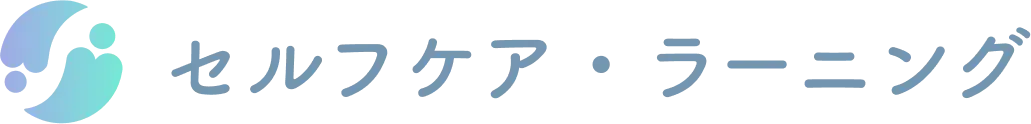職員間のコミュニケーションが園運営に与える影響
現場では日々、職員さん同士のコミュニケーションが行き交っています。
それらは、子どもたちが過ごす空間を作り上げています。
そもそもコミュニケーションの取り方は、
学校等で習うことなく、自然と身につけたものですよね。
私たちはみんな、子どもの頃に周囲の人たちを見て、
どのように振舞うかを覚えてきたのだと思います。
その後も大人になる過程において、
成功と失敗の両方を体験しながら、
「こうするといい」「こうするとよくない」と学習してきました。
学習した結果、
みんなが「良好なスタイル」になれば理想なのですが、
そうはいきません。
どのようなスタイルになるのかは、人それぞれ異なるわけです。
なにせ、遺伝や気質、性格も影響しますからね。
では、
どんなスタイルが保育士に向いているのでしょうか。
どんなスタイルがチームワークに貢献するのでしょうか。
この答えは、職場の安定運営に直接的に影響することでしょう。
職員が定着しない、業務効率があがらない、一体感が生まれないなど・・。
あらゆる問題について、
コミュニケーションの取り方が大きな要因となっていますから。
失敗例・成功例に共通するポイント
私は実際に現場起きた失敗例も成功例も数多く見聞きしてきました。
そこにはかなり大きな共通点があります。
すべての職員さんにとって、この共通点を知ることは有益です。
どんな育ち方をして、
どんなスタイルを身につけた人でも、
変えられる部分があるからです。
大きな変化を起こすことは難しいですが、
小さな変化を起こすことは誰にでも可能です。
長年のスタイルは変えにくいからこそ研修が必要
しかし、
人は長年使ってきたスタイルを、
そう簡単には変更できないものですよね。
「もっと受け取りやすい言い方をしないと・・」
「もっとはっきり伝えないと・・」
「もっと助け合える関係を作らないと・・」
そう願うものの、
自分が長年使ってきたコミュニケーション方法では、
望む結果にならないことが多々あるのです。
ですから、研修担当者のみなさんも、
法人内のどなたかに対して、
「どうしてあんなコミュニケーションをしてしまうんだろう?」という想いを、
抱くことがあるのではないでしょうか。
相手を変えることができれば楽ですが、
残念ながら、そうはいきませんね。
自分のスタイルを変えるには、
自分がそれを選択するしかありません。
振り返りと実践を繰り返す場が研修の役割
いままでどうだったかを振り返り、
その長所と短所の両方を理解して、
新しい行動へ置き替えていく。
そのきっかけ作りが「コミュニケーション研修」であると言えます。
計画的かつ継続的に、適切なコミュニケーションについて学ぶこと。
振返り、気づき、知って、体験して、日常で実践すること。
この繰り返しが「せめて年1回」は必要ではないでしょうか。
コミュニケーションを学ぶ場がなければ、
あっという間にもとの習慣に戻っていくことは明らかです。
いかがでしょうか。
まずは最初の一歩をどう始めるか?
共に考えてみませんか?
こちらで無料相談を受け付けています。
また最初の1歩をどう始めるか?
こちらの記事でもお読みいただけます。
今回はコミュニケーション研修を取り入れる意義についてお話ししました。
次回以降では、年間計画の検討の仕方について、
ポイントを整理してお伝えしていきます。