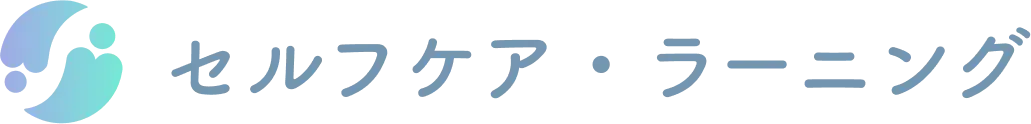コミュニケーション研修の第一歩をどうするか?
前回の記事では、
保育士の「キャリアアップ」の意味に触れて、
「コミュニケーション力」が専門性の1つであることをお話ししました。
「コミュニケーション力」が専門性の1つであるとすれば、
ぜひ計画的、継続的な研修計画に盛り込みたいものですね。
もし研修担当のあなたが、
はじめてコミュニケーション研修の導入を企画するのであれば、
最初の一歩をどうしようと思いますか。
コミュニケーション研修の導入は2つの方法から始められる
私はすでに80社以上の保育園運営会社と関わってきましたが、
導入のパターンには大きく分けて2種類あります。
- 最初からシリーズ研修として導入する
- まずは1回だけ試験的に実施する
また、最初の実施対象をどうするかという点でも、
大きく分けて2種類あります。
- 特定の階層に対して実施する
- 職員全員が集まる会で実施する
特定の階層の場合、もっとも多いのは、
園長・主任といった管理職を対象にするケースです。
最初からシリーズとするか、まずは1回だけとするか。
ここは予算と現場の状況、企画のタイミングなどで違ってきます。
職員全員が集まる会で実施する場合は、
毎年行われている全社ミーティングのプログラムに組み込むケースや、
年1回の全体研修会を「コミュニケーション研修」とするケースがほとんどです。
シリーズ研修として導入する場合の特徴とメリット
• 特徴:数年継続を前提に、体系立てたカリキュラムを組める
• メリット:習慣化しやすく、段階的にスキルアップできる
• 懸念点:初期費用やスケジュール調整のハードル
• 企画のポイント:「継続学習で行動変化を生みたい」場合に効果的
まずは1回だけ試験的に実施する場合の特徴とメリット
• 特徴:単発でやってみて反応を確認できる
• メリット:参加者の声を聞き、次の企画につなげられる
• 懸念点:一度きりで終わると定着しないリスクがある
• 企画のポイント:「まずは小さな一歩を踏み出したい」場合に有効
どちらの方法でも大切なのは「初回の満足度」
2つの始め方を整理してみましたが、いかがでしょうか。
あなたの法人では、どちらの選択があっているでしょうか。
いずれにせよ、参加者の「初回の満足度」が最重要だと私は思います。
「初回の満足度」が高ければ、
「もっと知りたい」「また受けたい」という声が必ず上がってきます。
その声が、次回以降の企画を後押ししてくれるでしょう。
各社の研修担当者さんも、
この「初回の満足度」にとても注目していて、
内心ドキドキしている方も少なくないようです。
そして「初回の満足度」を高くして、
さらに「継続への期待」を持ってもらうには、
やはりいくつか「はずせないポイント」があります。
次回の記事では、その点を書いていきますので、
ぜひ続けてお読みくださいね。